実は二年ほどオンラインでカウンセリングを受けている。
カウンセリングを受けていることを大っぴらにするのは、なんだか自分の恥部をさらけ出すかのようで恥ずかしかった。
でも、なかなかブログに書くこともないし、恥ずかしいとか言ってないで、何でもかんでも書いてしまえ。そう思ったので、これからは、カウンセリングで話したことをざっくりと記録していこうと思う。
今回の内容は、私の敵「回避型コーピング」について。回避型コーピングとは何か。回避型コーピングに頼り切りになってしまう理由や成り立ち、そして最終的にはどうしていくのがよいのか。
最後には、次回までにやっておく「宿題」も紹介しよう。
まずは私の敵である「回避型コーピング」について――
私の敵は「回避型コーピング」
「回避型」と聞いて私がまっさきに思い浮かべるのは、大人気ハンティングアクションゲームの「モンスターハンター」に登場する武器である、ランスだ。
大型の槍と、これまた大型の盾を持った重厚感のある装備で、モンスターからの攻撃をその大きな盾で受け、槍でもって弱点を突くのだ。
ランスを装備していると動きが遅くなるので、基本的にはモンスターの攻撃を回避することはないが、稀に歴戦の猛者が「回避ランス」と呼ばれる変態的な立ち回りを見せる。バックステップを巧みに利用し、闘牛士のようにモンスターの攻撃を回避して戦うのだ。
でも、ここで言う「回避型」とは、そんなかっちょいいものじゃない。
「コーピング」とは、ストレスに対処するための行動や方法、ストレスとどのように向き合うかという認知のプロセスを指す心理学用語だ。
そして「回避型」というのはコーピングのスタイルのこと。
つまり「回避型コーピング」とは、ストレスへの対処法として回避、すなわち「ストレス源を避ける」という方法をとることを言う。
この「回避型コーピング」こそが、私の最大の敵なのだ。
前提:回避が役立つときもある
2016年に放映されたテレビドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」じゃないけど、回避型コーピングが役に立つときもある。
大事なのは「ありとあらゆるコーピングが使える」こと。
コーピングの種類に優劣はない。ただしコーピングの選択に「偏り」があると、特定のストレスに対して非機能的なコーピングを選んでしまうことがあり、これが有害なのだ。
そんなわけで、必ずしも「回避型コーピングが悪である」とは言えない。
ようするに「手札は多いほうがいい」ということだ。
私の場合この「手札」が非常に少なく、回避型コーピングに偏っていることが、生きる上での大きな問題になっている。
ゆえに「私の」敵が回避型コーピングなのであり、あなたにとっての敵が何なのかは、あなた自身のコーピングの偏りを分析していく必要がある。
なぜ回避してしまうのか? 回避型コーピングの原因4つ
ここで紹介する4つの回避型コーピングの原因は、あくまで「私の」原因であり、同じく回避型コーピングに悩んでいるひとすべてに当てはまるものではない。
また、ここで紹介する4つの原因は、現在判明しているものに限る。ひょっとすると、まだ見つけられていないだけで、他にも原因があるのかもしれない。
原因1「対処不能スキーマ」
まず「スキーマ」について簡単に説明しよう。スキーマとは、過去の経験や知識の集合であり、これをもとに作られる「思考の枠組み」のことだ。
私は「世界への定義づけ」だと解釈している。
例えば青信号を見て進もうと思ったり、赤信号を見て止まろうと思うのは、親なり先生から「青は進め。赤は止まれ」と教わり、信号に対してそのような定義づけをするからだ。このような定義づけをスキーマと呼ぶ。
回避型コーピングの原因として最初に取り上げる「対処不能スキーマ」は、理由はさまざまあるけれども「自分はこの問題に対処できない」と自分に対しておこなった定義づけのことだ。
スキーマの根拠としては、自分には能力がないから(例えばテストの点数がいつも低いから)問題に対処できない、などがあげられるんだろう。
ようするに「自分には対処できない」という先入観により、対処せず回避するというコーピングを取りがちだということだ。
原因2「恥と失敗スキーマ」
小中学生の頃、同級生に上手くできなかったことをバカにされたり、からかわれたりした経験から「恥をかくくらいなら死んだほうがマシだ」のような強いレッテル貼りがおこなわれたんだろうと思う。
上手くいかなくて恥ずかしい思いをするかもしれないぞと思うと、やはり回避するというコーピングを取りがちになる。
原因3「何をしてもムダ(学習性無力感)」
こちらもまたスキーマということになるだろうけど、心理学的には「学習性無力感」と言ったりもするらしい。
それこそ学校でのイジメ経験が、私の学習性無力感のもとになっているんだろうと思う。
子供にできることは少ないと、オジサンになった私は思うわけだけど、小学生だった当時の私にはそんなことは関係ない。ただただ不当な扱いを受け、これを何とかしたいのだけど、どうしていいか分からない。あるいは手を尽くしてもどうしようもない。
そんな経験を何度も積み重ねることで「何をしてもムダ」ということを学習し無力感に襲われる。これが学習性無力感であり、おそらく私の中のスキーマのひとつでもある。
何をしてもムダであるという考えが根っこにあると、ストレスへの対処や、新しいことへの挑戦を避けようとしてしまう。
原因4「回避することで生き延びてきたという経験・自信」
前項「回避が役立つときもある」で書いたことが、時を経て、悪さをしている。そういう側面もあるんだろうと思う。
子供にできることは少ない。学校でイジメを受けていても、勝手に引っ越しをして、転校することはできない。弁護士に相談して法的に相手を訴えるようなこともできないし、イジメっ子がグループを作っている場合、相手を「ぶっとばす」ということも現実的ではない。
できることといえば、親や先生に相談することくらいだろうか。その大人たちが問題解決のために動いてくれなかった場合、子供にできるのは「ひたすら逃げる」ことだけなんじゃないか。
そういうわけで、私は逃げに逃げた。
「親のクレジットカードをもってこい。そうしなければ殺す」などと脅されていたときは、行ってきますと学校へ出かけたフリをして、近所のさびれた小さな社の裏で、自分の背丈ほどある高い草に紛れてやり過ごしていた。
子供の頃から虫が苦手だった私が、じめじめした薄暗い草の中に紛れてやり過ごしていたのだから、どれだけ切羽詰まっていたのかがよく分かるエピソードだと思う。
でも、そうすることでしか対処できなかったし、そうすることで場当たり的ではあるけれども対処をすることができた。
これはまさしく「回避が役に立ったとき」であり、私はこのときの「成功体験」を強烈に定義づけしてしまった。
これにより私は「ストレスに対し常に回避型コーピング選ぶ」と言っていいほどに偏ったコーピング・スタイルを確立したのだった。
たくさんの選択肢の中から自由に選べる状態が、最強
ストレスに対し常に回避型コーピングを選んでしまうのだから、反対に「回避しない」コーピングを選ぶようになれたら良い。というわけでもないらしい。
回避型コーピングは私の最大の敵だけれども、回避が効果的だという場面があるのも事実。
さっき書いたとおり「手札は多いほうがいい」のだ。
無数にある選択肢の中から自由に(できれば効果的に)コーピングを選べる状態が望ましい。そのためには「回避を含め」ありとあらゆるコーピングを選択できる柔軟なスキーマが必要不可欠だ。
目指すは「自由の土台」
カウンセラーさんがよく「土台」と言う。
土台という表現を借りるなら、私はありとあらゆるスキーマが「回避を促す方向」に働く、いわば「回避の土台」の上にいるんだろう。
クマに遭遇したときなど、回避が可能ならば回避を優先したほうがいい場面もある。しかし「手札に回避のカードしかない」という状態はよろしくない。
カードゲームにおいて、強いカードばかりを集めてデッキを組んでも、そのデッキが強いとは限らないのと同じで、選択肢のレパートリーとバランスが大切なのだ。
「挑戦」という言葉を見ると、なんだか前向きで、良い感じがする。だけど「手札に挑戦のカードしかない」という状態もまた、よろしくない。
バランスのよい手札を揃えて生きていくためには、バランスよくさまざまなコーピングを扱うことのできる「自由の土台」に移住したい。
宿題「コラム法」と「スキーマフレーズの検討」
宿題というわけではないのかもしれないけど、ふたつのワークシートの実践を継続している。それが「コラム法」と「スキーマフレーズの検討」だ。
コラム法(認知再構成法)
こちらはスキーマ療法というよりは認知行動療法(CBT)に用いられることの多い方法だ。と言いつつ、スキーマ療法は認知行動療法の延長線上にあるのだけど。
コラム法では、無意識の領域においてスキーマよりずっと表層にある「自動思考」を対象に分析をし、よりバランスのよい適応的な自動思考を模索していく。
自動思考とは、何か起こったときまっさきに頭をよぎる考えやイメージのことだ。
例えば「雨が降る」ことで「悲しい」という感情が出てきたとする。心理学では、そのとき頭の中で「雨が降っているので外へ遊びに行けないな」と考え、その結果「悲しい」という感情が発現しているのだ、と考える。
つまり、状況(雨が降る)があり、それに対して自動思考(外に遊びに行けない)が浮かび、結果として感情(悲しい)が発現する、ということだ。
もしも自動思考として「外に遊びに行けない」ではなく「この間買った新しい傘が使える」ということが思い浮かんでいたら、感情はむしろポジティブなものになっていたかもしれない。
必ずしもポジティブなのが良いというわけじゃないけど、少なくとも自動思考が変わることで感情や身体反応、行動などが変化するということだ。
この自動思考を、よりバランスの取れた(適応的な)ものに変化させようというのが、コラム法だ。
コラム法の詳しいやり方や実践する際のポイントについては、別の記事にまとめている。
書籍ならば以下のものがとっつきやすくておすすめだ。
スキーマフレーズの検討
スキーマフレーズとは、文字通り「スキーマを如実に表しているフレーズ」のことだ。より根源的な概念であるスキーマに対し、もう少し具体的なスキーマフレーズ、という感じだと思う。
無意識の領域の奥深くにある「スキーマ」より、もう少し手前にある「フレーズ」のほうが扱いやすい。だからスキーマフレーズを対象に、そのフレーズを持っているメリットやデメリットなど、多角的に検討してゆく。
「スキーマフレーズの検討」については、長くなるので後日に別の記事にまとめたいと思う。
おわりに
見切り発車で始めた「カウンセリングの記録」だけど、書いてみるとけっこうな文量になり驚いている。恥ずかしいと言いながらノリノリで自分語りをしているようで気に食わないけど、それも自分なんだろう。
初回なので、なるべく用語を丁寧に解説しながら書いたつもりだ。次回以降(もしもあるなら)はもっと短い記事になると思う。
そもそもカウンセリングというものの性質が「雑談をしつつその中から心のありように関係していそうなことを選び深堀りしていく」という感じなので、言い方は悪いが「無駄話」をしている時間も多かったりする。
私はそれを「ムダな時間だ」と感じてしまうことが多い。もっと有用で、手っ取り早く、人生が最高に幸せになる「魔法」のやり方を教えてくれよと思ってしまう。
現在はそれを「それだけ不当な扱いを受けてきたんだよなぁ」とか「自分にとっては普通のことだったかもしれないけど、けっこうしんどかったんだなぁ」と思えるようになってきた。
これはきっと良い兆候だ。
なんというか「社会に適応できない自分は死んだほうがいいんだ!」などと息を巻いているのは私だけで、カウンセラーさんも、一緒にカウンセリングを受けてくれている彼女も、そしておそらくこれを読んでいるあなたも「上手く適応できない部分がありながらも生きていくのが普通じゃんね」という具合に思っているようだ。
「完璧でなければいけない」と考えがちなのも、私のスキーマの成すところなんだろう。
ゆっくり時間をかけて、そういう偏りを緩めていくことが大事なんだろうなぁ。
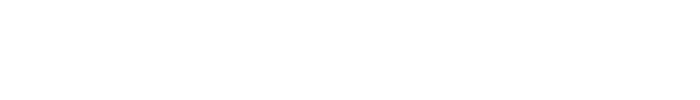

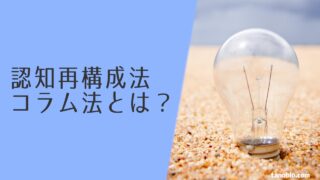


コメント