筆者は現在カウンセリングを受けており、そこで教わった認知再構成法のひとつ「コラム法」を日々実践している。
この記事では、コラム法を実践しているひとりの人間として、コラム法の基本的なやり方やポイント、取り組むときの心構えなど実践的なところについて、自分なりに解説してみようと思う。
コラム法(認知再構成法)とは
コラム法とは認知行動療法やスキーマ療法における認知再構成法のひとつだ。コラムを用いて自動思考やスキーマの発見、分析をし、よりバランスの取れた考え方を導き出すためのツールである。
コラム法(認知再構成法)のやり方
コラム法では、ひとつひとつの出来事について、7つの項目を記入しながらよりバランスの取れた考え方を目指していく。
注意してほしいのが、この「バランスの取れた考え方」というのは、ポジティブだから良いとかネガティブだから悪いというような二元論的なものではないということだ。
ポジティブな考え方をしたほうが良さそうだと感じるかもしれないけど、つねにポジティブな考え方をしていると、思わぬリスクに足をすくわれる、ということもあるかもしれない。反対に、つねにネガティブな考え方をしていると、チャンスを掴み損ねる、なんてこともあるだろう。
目指すのはポジティブでもネガティブでもない、バランスの取れた「フラットな考え方」だ。
コラム法を実践することで、以下のようなことを実感できるといいと思う。
- 物事にはいろいろな考え方(捉え方)がある。
- 自分の抱いた第一印象(自動思考)より、もっと適応的な考え方(捉え方)がある。
繰り返しになるけれど、コラム法は第一印象とは違う他の考え方を模索するためのもので、ポジティブだから良い、ネガティブだから悪いなどと決めつけるものではない。
私はこの点を勘違いしていた。
コラムを記入すると「いつもネガティブな考えばかり思い浮かぶ私は不適応的で、だから人生が上手くいかないんだ」などと考え、余計にネガティブな感情を深めてしまうことがあった。
コラム法は思考の良し悪しを評価するものではなく、もっと別の考え方を探してみよう、という探求に近い。
コラム法で記入する7つの項目は、以下のとおりだ。
- 状況(対象とする出来事をなるべく詳細に)
- 気分(その時の気分と、その点数)
- 自動思考(その状況に対する第一印象)
- 根拠(その第一印象が思い浮かんだ根拠・理由)
- 反証(その第一印象とは相容れない根拠や事実)
- 適応的思考(よりバランスの取れた考え方を模索する)
- 気分の変化(適応的思考を考えることで生じた気分の変化)
状況
コラム法では一般的に「不快な感情を伴う出来事」を扱う。だから例えば「悲しい」とか「イラッとした」とか「モヤモヤするわぁ」といった感情が出てきたら、その感情の原因となったであろう出来事や、その状況を書く。
ポイントとしては、後で見返した場合でも当時の状況がありありと伝わってくるように、なるべく詳細に書くことだ。
完璧を求める必要はないけど、5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのようにして)に沿った書き方をしておくと、見返したときも思い出しやすい。
気分
その出来事、状況において生じた気分と、その強度を点数にして書く。例えば「怒り 70点」のように書けばいい。こちらもより詳細なニュアンスが伝わるように書けたらより良いけど、そんなにこだわらなくてもいい気がする。
大きく分ければ「怒り」だけど、これは「苛立ち」だとか、これは「腹立たしい」気持ちだとか、なんとなくパッと出てきた言葉でいいと思う。
自動思考
その出来事、状況に対する第一印象。例えば最初に考えたことやイメージなど。それが自動思考だ。心理学では「自動思考によって気分が変化する」と考えられているので、この自動思考をうまく捉えて言語化することが非常に大切である。
コラムを丁寧に書いているような時間がない場合でも、自動思考だけはメモをとっておきたい。とりあえずこれさえあれば、少し時間が空いてしまってもコラム法を実践できると思う。
あるいは「気分」のほうから「そういえばあのとき、こんなふうに思ったんだよなぁ」と自動思考を逆算するように思い出せたりもするから、気分も一緒に書いておけたら、かなりいい。
コラム法では、この自動思考を元に「もっと他の考え方もできるんじゃないか?」と模索していくことになる。
根拠
この項目では、先程の自動思考を生じさせた根拠を書く。
「根拠」というと少し堅苦しいから、わかりやすく「理由」と考えてみてもいいかもしれない。ただし、根拠の項目ではできる限り「事実」を扱うようにしたい。
誰にでも「思い込みを根拠にしてしまう」ということもあるし、認知の歪みと呼ばれるバイアスには「根拠のない決めつけ」というものもあるけれど、ここではなるべく事実を書こう。
事実だけを選別して書くことで「どうやら自分の思い込みや決めつけにより自動思考が生まれている部分もありそうだ」ということに気がつくこともある。この気付きはけっこう大事だと思う。
反証
生じた自動思考に矛盾する事実を書く。
こちらも「なるべく事実を書く」という意識でいいと思う。
不快な感情を伴う出来事が起こり、すぐにコラムを書いているような場合では、視野が狭くなっていて自動思考に矛盾する事実というものが見えなくなっていることもある。そういうときは「ひょっとしたらこういうこともあり得るか?」というような曖昧なことを書いてしまってもいいと思う。
適応的思考
根拠と反証をよく見比べて、最初に浮かんだ自動思考よりバランスの取れた考え方はできないかと、新しい考え方を模索し、その結果を書く。
「適応的」というと、私のように「自分は不適応的なダメ人間だ」などと考えてしまうひともいるかもしれない。あくまでも「もっと別の考え方を探してみよう」という思いでやるのがいい。メンタルヘルス改善するための手段なのに、より落ち込んでしまっては元も子もない。
もうひとつ「無理やりポジティブな思考を探そうとする必要はない」ということも、頭の片隅に置いておきたい。これまた私がやりがちなヤツ。
目指すべき思考があるとするなら、それは変にポジティブでもネガティブでもない、事実をベースにしたフラットな考え方だ。
気分の変化
ここまでコラムを書いてきて、現在の気分は変化しただろうか。「気分」で書いたのと同じように、気分とその点数をつけよう。
新しい考え方を見つけることで嫌な感情が少しでも減っていれば、コラム法は大成功だ。
おわりに
コラム法(認知再構成法)を実践するひとりの人間として、自分なりにやり方を解説してみた。私自身まだ「別の考え方」を模索している最中なので、ひょっとしたらまた付け加えたいことが出てくるかもしれない。そういうときはこっそり追記していこうかな。
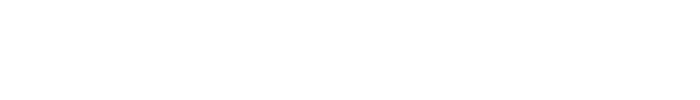
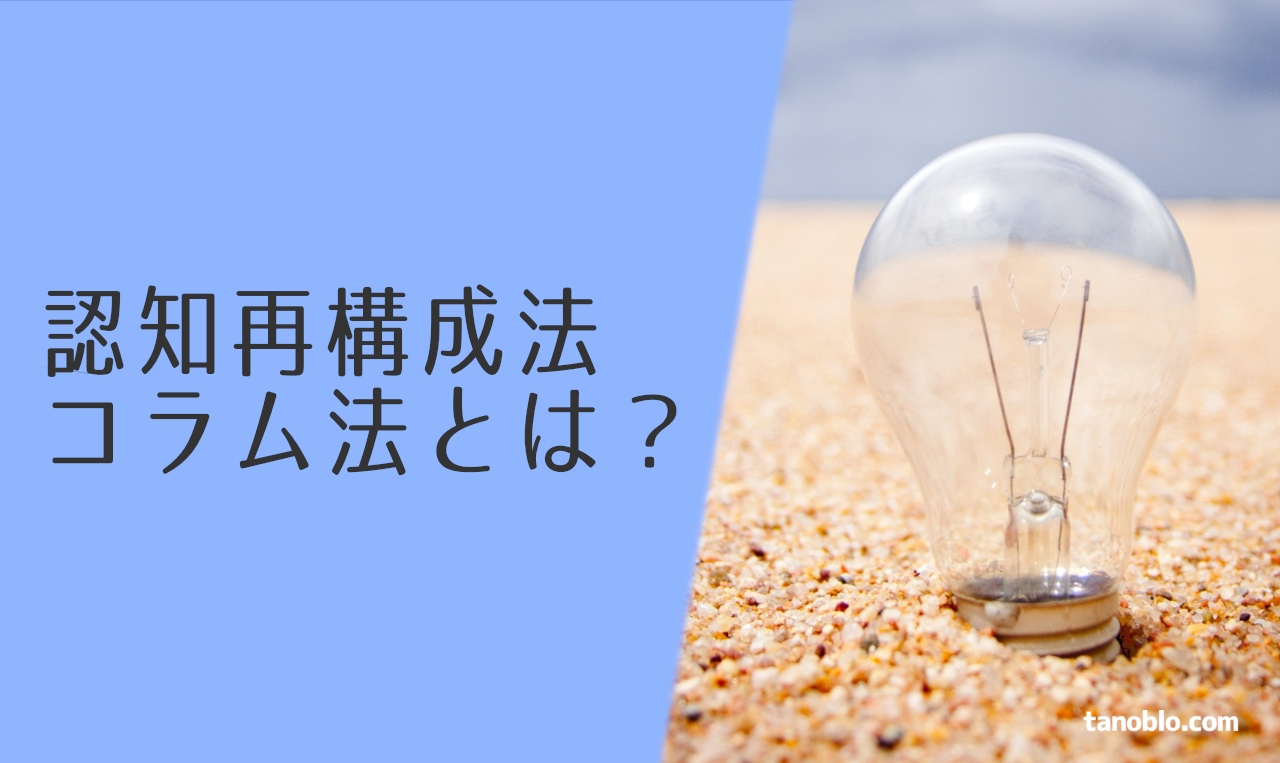

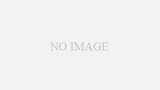
コメント